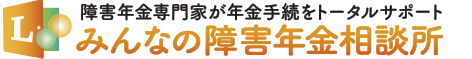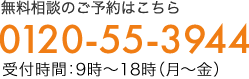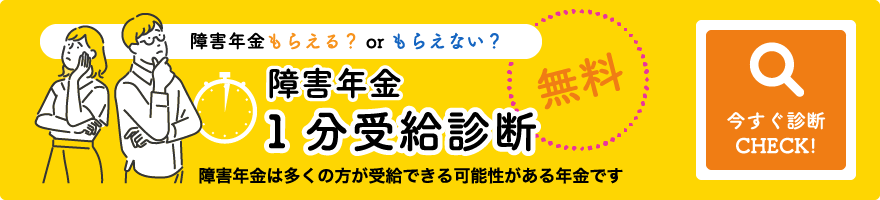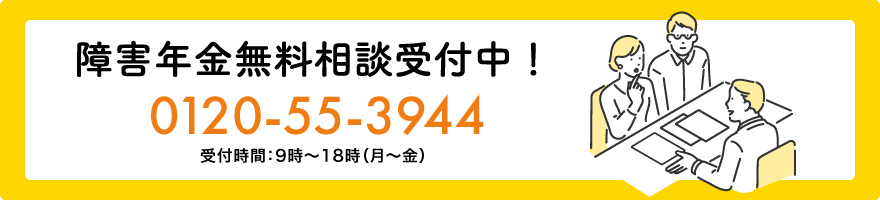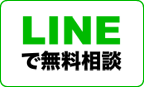お知らせ 2025.06.18
PTSDと障害年金申請の手引き・診断から申請までを解説
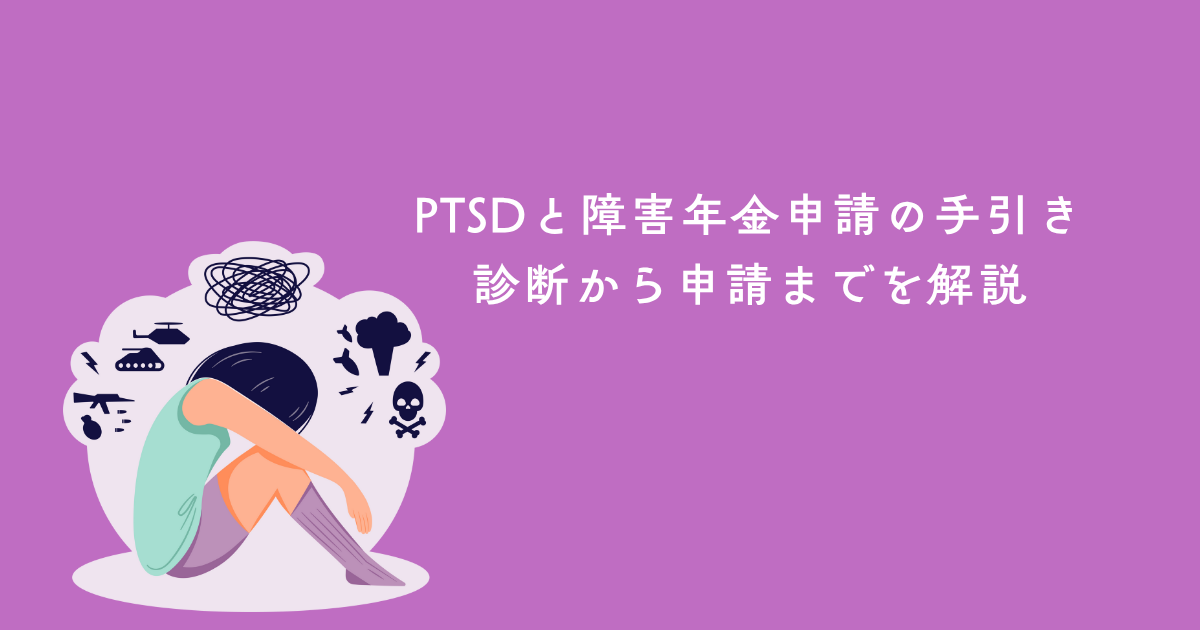
心の傷を抱え、日々の生活に困難を感じている方へ。
将来への不安、そして障害年金制度への疑問を一人で抱え込んでいるかもしれません。
今回は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と障害年金について、申請の手順や注意点などを解説します。
少しでも不安を解消し、未来への一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。
PTSDと障害年金の関係性
PTSD単独での障害年金
PTSDは、それだけでは障害年金の対象とはなりません。
神経症性障害に分類され、障害年金制度では原則として認定対象外とされています。
しかし、これは絶対的なものではなく、個々の症状や日常生活への影響を総合的に判断されます。
併発疾患と障害年金
PTSDと他の精神障害(うつ病、統合失調症など)を併発している場合は、障害年金の対象となる可能性が高まります。
複数の病名がある場合は、診断書に全て記載してもらうことが重要です。
医師には、症状の詳細や日常生活への影響について丁寧に説明し、適切な診断を受けましょう。
日常生活への支障と年金
障害年金の認定は、日常生活への支障の程度が大きく影響します。
具体的には、食事、身辺の清潔保持、金銭管理、通院、人間関係、安全確保など、日常生活の様々な場面における困難さを医師に伝え、診断書に反映させる必要があります。
例えば、フラッシュバックによるパニック発作で外出が困難になったり、集中力の低下で仕事が続けられなくなったりするといった具体的な事例を医師に説明しましょう。
日常生活における困難さを客観的に示す証拠(例えば、治療記録や通院記録など)も有効です。

障害年金申請の手続きと注意点
医師との連携の重要性
医師との綿密な連携は、障害年金申請の成否を大きく左右します。
定期的な受診を行い、症状の変化や日常生活への影響を継続的に医師に伝えましょう。
疑問点があれば、遠慮なく医師に質問し、理解を深めることが大切です。
診断書の適切な記述
診断書には、PTSDだけでなく、併発疾患や日常生活への支障についても詳細に記述してもらう必要があります。
特に、日常生活の具体的な困難さや、それがPTSDによって引き起こされていることを明確に記載してもらうように医師にお願いしましょう。
曖昧な表現ではなく、具体的なエピソードを交えた記述が重要です。
例えば、「買い物に行けない」だけでなく、「フラッシュバックが起きやすく、人混みを避けられないため、一人で買い物に行くことが困難である」といったように具体的に説明してもらうことが効果的です。
申請書類の準備と提出
申請書類は、年金事務所から送られてくるもの以外にも、医師の診断書や、必要に応じて他の書類(例えば、雇用保険の受給資格喪失証明書など)が必要となる場合もあります。
提出期限を守ることはもちろん、書類に不備がないよう、事前にしっかりと確認することが重要です。
申請後の流れと注意点
申請後、年金事務所から審査結果の通知が届きます。
もし不支給であった場合でも、諦めずに再申請を検討することもできます。
その際は、前回の審査結果を踏まえて、より詳細な情報を提供する必要があるかもしれません。
専門機関に相談することも有効な手段です。

まとめ
PTSD単独では障害年金の対象とならない場合が多いですが、併発疾患や日常生活への支障の程度によっては、受給できる可能性があります。
申請にあたっては、医師との綿密な連携が不可欠であり、診断書には症状や日常生活への影響を具体的に記載してもらうことが重要です。
申請書類の準備や提出、申請後の流れについても、しっかりと理解しておきましょう。
もし、手続きに不安がある場合は、専門機関への相談も検討してみてください。
障害年金は、権利です。
諦めずに、一歩ずつ進んでいきましょう。