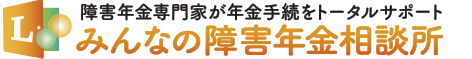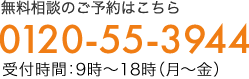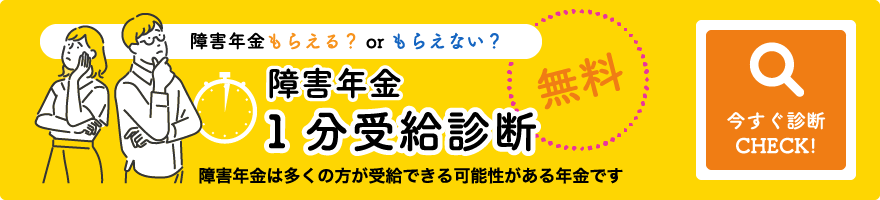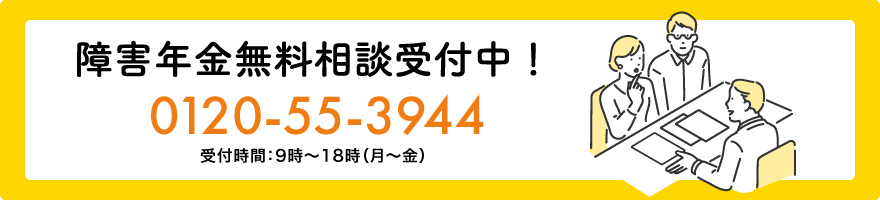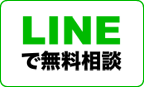お知らせ 2025.07.18
ベーチェット病で障害年金を受給するには?診断書作成のポイント

ベーチェット病の診断と日常生活は、人それぞれ大きく異なります。
そのため、障害年金申請の可否も、個々の状況によって大きく変わるでしょう。
申請にあたり、重要なのは正確な情報を基に、適切な手続きを進めることです。
しかし、複雑な手続きや専門用語に戸惑う方も少なくありません。
このガイドでは、ベーチェット病と障害年金の関係性、特に診断書の書き方について、具体的な情報を提供します。
申請を検討されている方は、ぜひ最後までお読みください。
ベーチェット病と障害年金
障害年金の概要と受給要件
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出ている場合に支給される公的な年金です。
受給には、初診日、保険料納付期間、そして障害の程度といった要件を満たす必要があります。
初診日は、初めて医師の診断を受けた日です。
国民年金または厚生年金の加入期間中に初診を受けていることが条件となります。
また、一定期間以上の保険料納付も求められます。
そして最も重要なのは、ベーチェット病による障害が日常生活に著しい支障を及ぼしているかどうかです。
この点は、医師の診断書によって判断されます。
ベーチェット病の症状と等級判定
ベーチェット病は、口内炎、皮膚病変、関節炎、眼の炎症(ぶどう膜炎)など、多様な症状が現れます。
障害年金の等級は、症状の重さと日常生活への影響を総合的に判断して決定されます。
例えば、視力の著しい低下や、日常生活動作の著しい困難を伴う場合は、1級または2級に該当する可能性があります。
関節炎による歩行困難など、日常生活に著しい支障がある場合も、高い等級が認められる可能性があります。
一方、症状が比較的軽度で、日常生活への影響も少ない場合は、3級となるか、そもそも受給対象外となる可能性があります。
申請に必要な書類と手続き
障害年金申請には、申請書、診断書、保険証などの書類が必要です。
申請書は、お住まいの市区町村の年金事務所で入手できます。
診断書は、主治医または専門医に依頼します。 診断書には、ベーチェット病の診断、症状の詳細、日常生活への影響、治療内容などを正確に記載してもらう必要があります。
申請手続きは、年金事務所で行います。
審査には数ヶ月かかる場合があり、必要に応じて追加の検査や調査が行われることもあります。

診断書の書き方とポイント
医師への説明ポイント
医師にベーチェット病の症状について説明する際には、具体的な症状の頻度や程度を明確に伝えましょう。
例えば、「口内炎は月に何回程度でき、どのくらいの期間続くのか」「関節痛はどの程度の強さで、どのくらいの期間続くのか」「視力はどの程度低下しているのか」などを具体的に説明することが大切です。
また、症状によって日常生活にどのような支障が生じているのかを具体的に説明することも重要です。
例えば、「家事や仕事に支障がある」「外出が困難である」「痛み止めを服用しても痛みが改善しない」などを説明することで、医師が症状の重症度を正確に把握し、診断書に反映しやすくなります。
診断書に記載すべき症状
診断書には、ベーチェット病による全ての症状を網羅的に記載してもらうことが重要です。
口内炎、皮膚病変、関節炎、眼の炎症だけでなく、消化器症状、神経症状、血管炎など、全ての症状について、頻度、持続期間、程度を具体的に記載してもらうようにしましょう。
また、症状によって日常生活にどのような影響が出ているのかを具体的に記載してもらうことも重要です。
例えば、「歩行困難」「家事困難」「就労困難」など、具体的な影響を記載してもらうことで、審査官が日常生活への支障を正確に理解しやすくなります。
専門医への相談と診断書の依頼
ベーチェット病は、専門医の診察が必要な疾患です。
特に、眼の症状や血管炎など、重篤な合併症を伴う可能性があるため、専門医(リウマチ科医、眼科医など)への受診が推奨されます。
専門医に診断書の作成を依頼する際には、障害年金申請のためであることを伝え、症状の程度や日常生活への影響について詳しく説明しましょう。
必要に応じて、過去の検査結果や治療経過なども提示するとよいでしょう。

まとめ
ベーチェット病による障害年金申請は、複雑な手続きと専門的な知識が必要となります。
しかし、適切な診断書と準備によって受給の可能性を高めることができます。
この記事でご紹介したポイントを参考に、医師と十分に相談し、正確な情報を基に申請を進めていきましょう。
診断書には、症状の頻度・程度・日常生活への影響を具体的に記載してもらうことが重要です。
専門家のサポートを受けるのも有効な手段です。
生活を支えるための制度を、有効に活用しましょう。