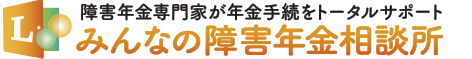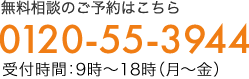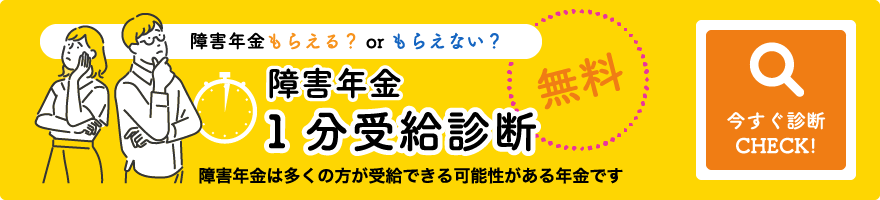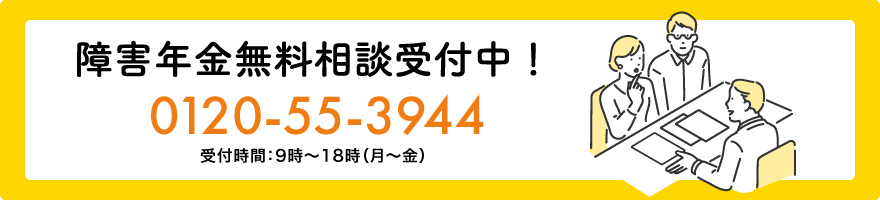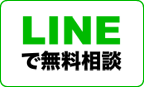お知らせ 2025.08.01
双極性障害で障害年金はもらえる?申請方法と受給までのステップ

双極性障害と診断され、日々の生活に不安を感じている方へ。
将来への漠然とした不安を抱えながら、どうすればいいのか悩んでいるのではないでしょうか。
もしかしたら、障害年金制度が、その不安を解消する糸口になるかもしれません。
経済的な不安から解放され、治療に専念できる環境を手に入れるための第一歩を踏み出してみませんか?
今回は、双極性障害と障害年金申請について、申請方法や重要なポイントを解説します。
少しでも不安が軽減されるよう、具体的な情報を提供していきます。
双極性障害と年金申請
日常生活能力の判定基準
双極性障害による障害年金の等級判定では、日常生活能力の判定が非常に重要です。
具体的には、食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達及び対人関係、身辺の安全保持及び危機対応、社会性といった7つの項目について、それぞれどの程度自立して行動できるかを評価します。
これらの項目において、どの程度困難を抱えているかを正確に医師に伝え、診断書に反映させることが大切です。
例えば、うつ状態では家事が全くできない、躁状態では衝動買いをしてしまうといった具体的なエピソードを医師に伝えることで、より正確な評価につながります。
日常生活における具体的な困りごとを事前にメモにまとめておくことも効果的です。
初診日の証明方法
障害年金申請には、双極性障害の症状で初めて医師の診察を受けた日(初診日)の証明が必要です。
初診日が特定できない、またはカルテが破棄されているといったケースも少なくありません。
しかし、初診日の証明方法は、必ずしもカルテだけではありません。
他の医療機関の診断書や、薬局の処方箋、通院記録など、様々な資料を組み合わせることで初診日を証明できる可能性があります。
もし、初診日の証明に困難を感じている場合は、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。
症状の波と就労状況
双極性障害は、躁状態とうつ状態を繰り返すのが特徴です。
申請においては、症状の波を正確に伝えることが重要です。
単に「気分が落ち込む」だけでなく、具体的な症状(例えば、睡眠障害、食欲不振、集中力の低下など)や、その症状が日常生活や仕事にどのような影響を与えているかを詳しく説明することが求められます。
また、就労状況についても、単に「働いている」「働いていない」だけでなく、具体的な内容(例えば、職種、勤務時間、職場の配慮など)を伝えることが重要です。
例えば、障害者雇用で短時間勤務をしている場合や、一般企業で勤務時間短縮などの配慮を受けている場合などは、その状況を具体的に説明することで、労働能力の低下が認められる可能性が高まります。

障害年金の受給ポイント
申請に必要な書類
障害年金申請に必要な書類は、診断書、病歴・就労状況等申立書、年金手帳などです。
特に診断書は、医師が状態を正確に記述したものでなければなりません。
そのため、医師への説明を十分に行い、症状や日常生活への影響を正確に伝えられるよう心がけましょう。
病歴・就労状況等申立書は、症状の経過や就労状況を具体的に記述する書類です。
曖昧な表現ではなく、具体的なエピソードを時系列で記述することで、審査官が状況を理解しやすくなります。
申請手続きの流れ
申請手続きの流れは、申請書類の提出、審査、支給決定という流れになります。
申請書類は、お住まいの地域の年金事務所に提出します。
審査には数ヶ月から一年以上かかる場合もあります。
審査期間中は、定期的に年金事務所から連絡がある場合もありますので、連絡先を正確に伝え、連絡を確実に受け取れるよう準備しておきましょう。
不安解消のための情報
障害年金申請は、手続きが複雑で、不安を感じる方も多いです。
しかし、一人で抱え込まず、専門機関や相談窓口に相談することをお勧めします。
また、インターネット上にも、障害年金に関する多くの情報が公開されています。
これらの情報も有効活用することで、申請への不安を軽減できるでしょう。

まとめ
双極性障害による障害年金申請では、日常生活能力の判定と初診日の証明が非常に重要です。
症状の波や就労状況を正確に伝えるため、医師への説明を十分に行い、具体的なエピソードをメモなどにまとめておくことが有効です。
申請手続きは複雑なため、不安な場合は専門家のサポートを受けることをお勧めします。
障害年金は、安心して治療に専念し、安定した生活を送るための制度です。
制度の活用を検討し、少しでも不安を解消しましょう。